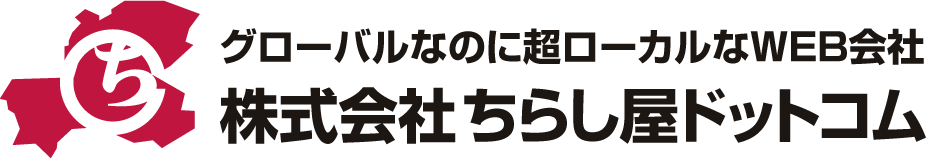ECサイトの裏側でアナログ業務が残っている可能性

聞いてください。先日、とあるECサイトで買い物をしたんですけど、なんと商品が間違って届いちゃったんですよ。
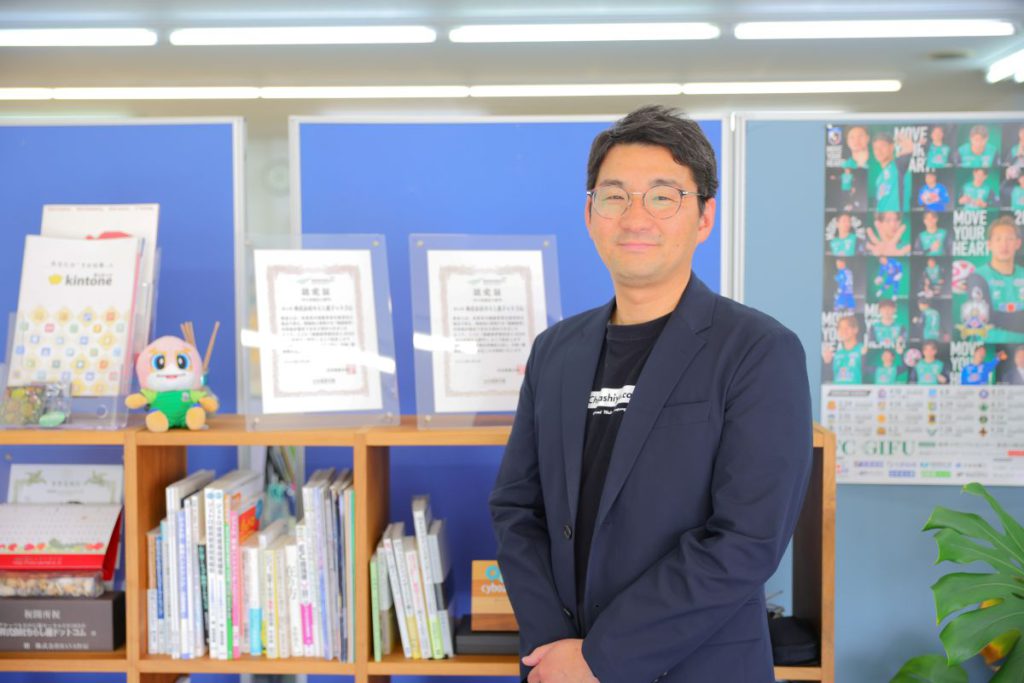
あら、それは困ったね。その後どうしたんですか?

商品が違うので、もちろんすぐに連絡をして正しい商品を送ってもらうことにしました。そして、その間違って届いてしまった商品を返送したんですよね。
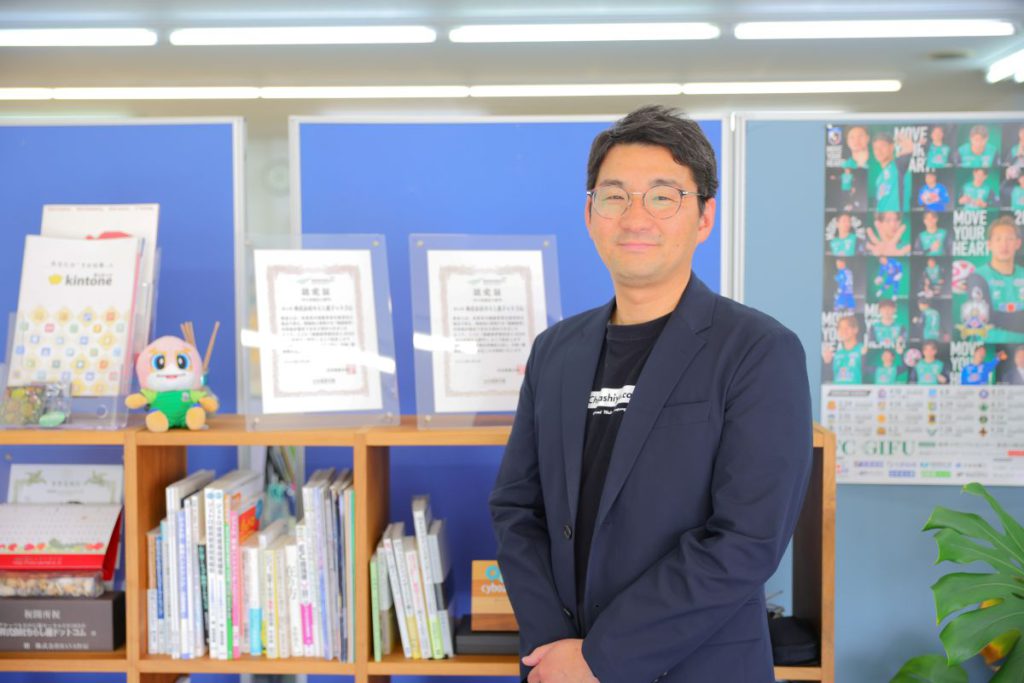
そうだよね~。
そういうことがあるとお互いにまた手間がかかるよね。
でもひょっとするとそのECサイトでは、裏側、つまり運営管理側においては業務をアナログ的にやってらっしゃる可能性があるね。

業務がアナログというと、それはつまりどういうことでしょうか?
アナログ業務によるミスの発生
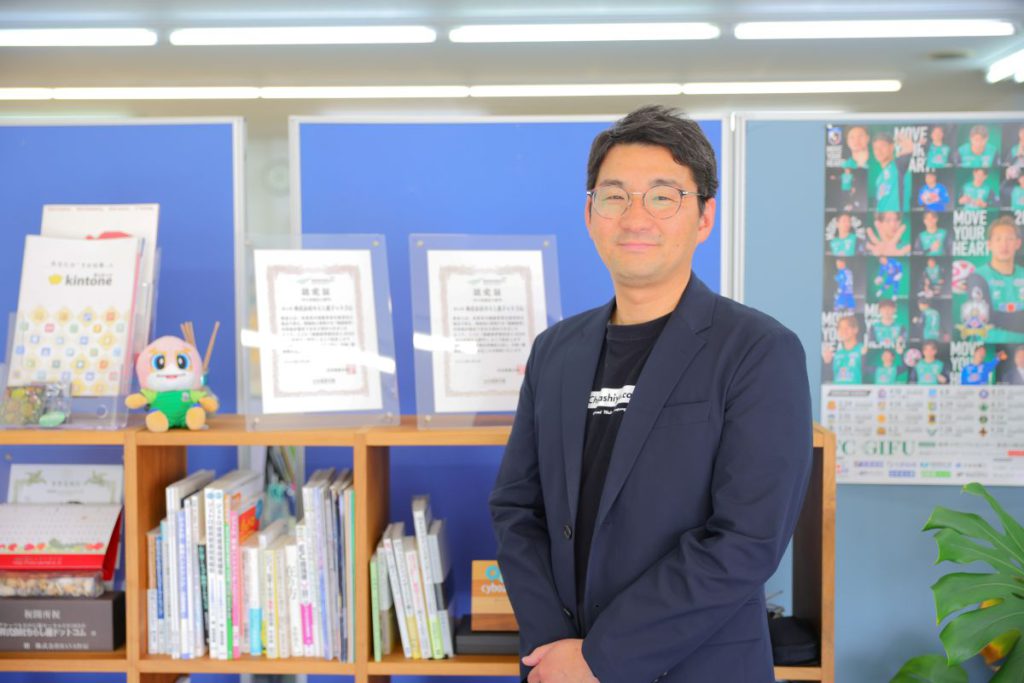
そうですね~。例えばなんですが、
ECサイトでは当然ですが、お客さんから注文が入った後に、その売れた商品を発送するために工場とか倉庫に「この商品を出荷してください」というような形で、いわゆる出荷指示を出すことがほとんどだと思います。
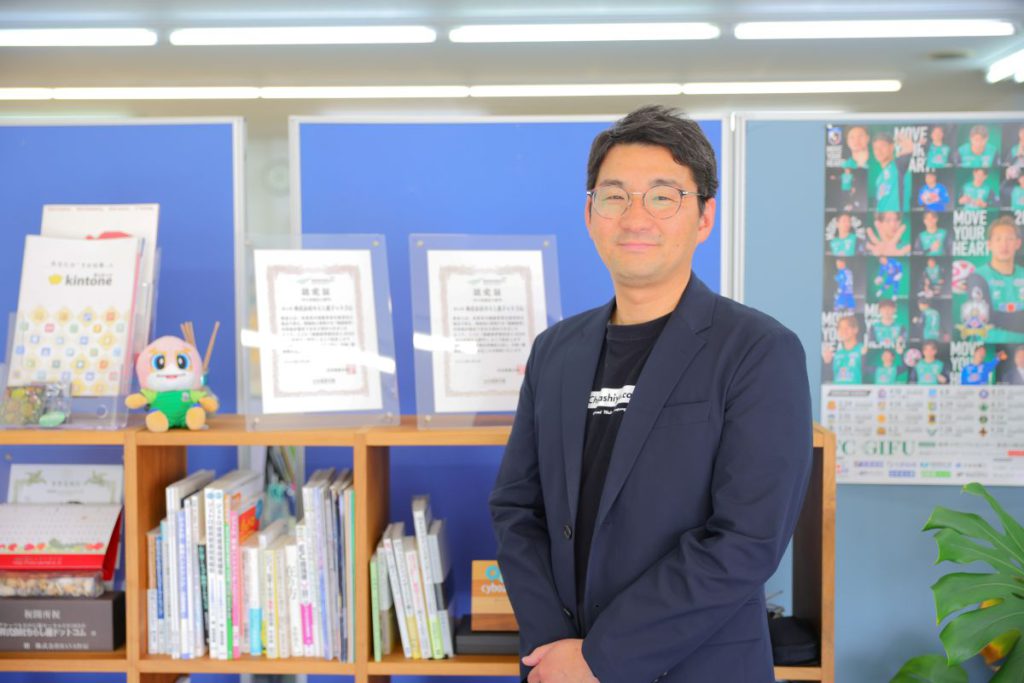
もちろんAmazonとか、楽天とか、あと大手のサイトなどはもちろん注文から発送の指示までは自動化されてることがほとんどだと思うんです。
ただ、これが中小企業さんが運営するECサイトだとアナログなやり方の業務となっていて、ひょっとすると発注の内容をもに、わざわざ例えばExcelで出荷指示書を作成している可能性がありますね。

なるほど。ただ、そのやり方だとなぜ間違った商品が届くことにつながるんでしょうか?
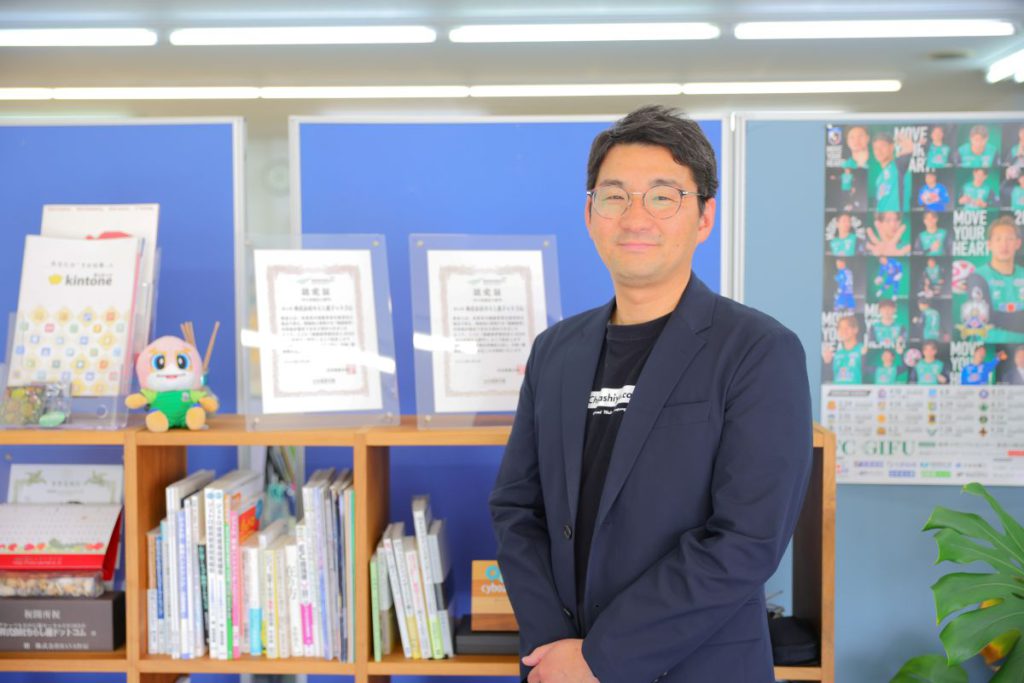
だってさ、小松君。
そのECサイトで注文が入った内容をわざわざExcelに手入力するってなると、これまた入力ミスが起こったり漏れがあったり数量間違えたりというミスの発生につながるじゃないですか。

ああ、なるほど。そういうことですね。
その情報を元に手入力したり(手書きがあるかも)、やっぱり業務がアナログだとそういったミスにも繋がるかもしれないですね。
ではそれは『BtoB』の現売でも同じなんでしょうか?
電話やFAXでの受発注のアナログ業務
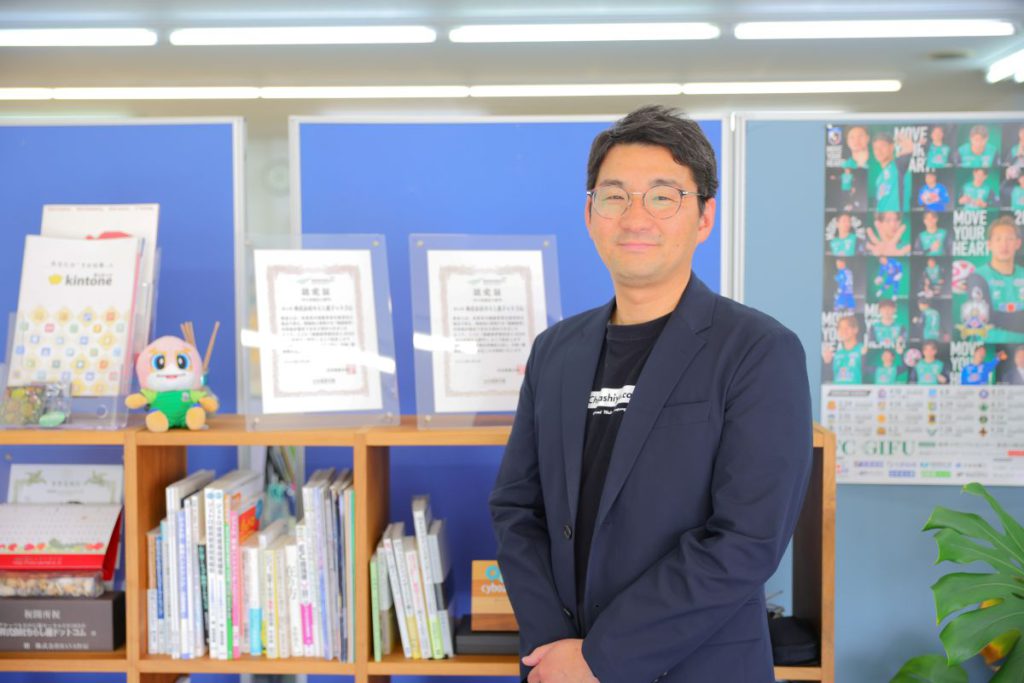
そうだね。アナログな業務をしているところはまだまだあると思います。
ですので、今回は、受注データをもとに出荷指示書のような次の業務の指示書を自動で出すといった機能を含めて『BtoB EC』を導入すると業務フローが自動化していくんです!というテーマで、動画を進めていきたいと思います。
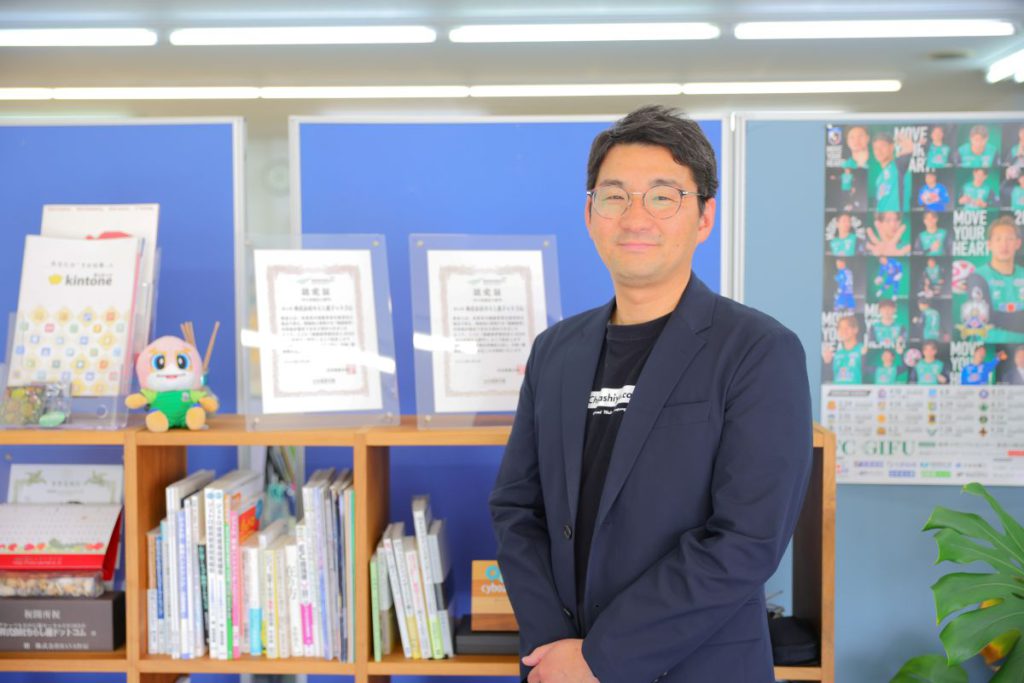
小松君、ちょっと質問なんですけど、先ほどまでお話ししてきた内容はECサイトからの注文を前提に話をしてきたんですが、これまでの動画でよく説明をしてきたアナログな受発注といえばどんなものでしたっけ?

アナログ受発注といえば、「電話とFAX」ですね。
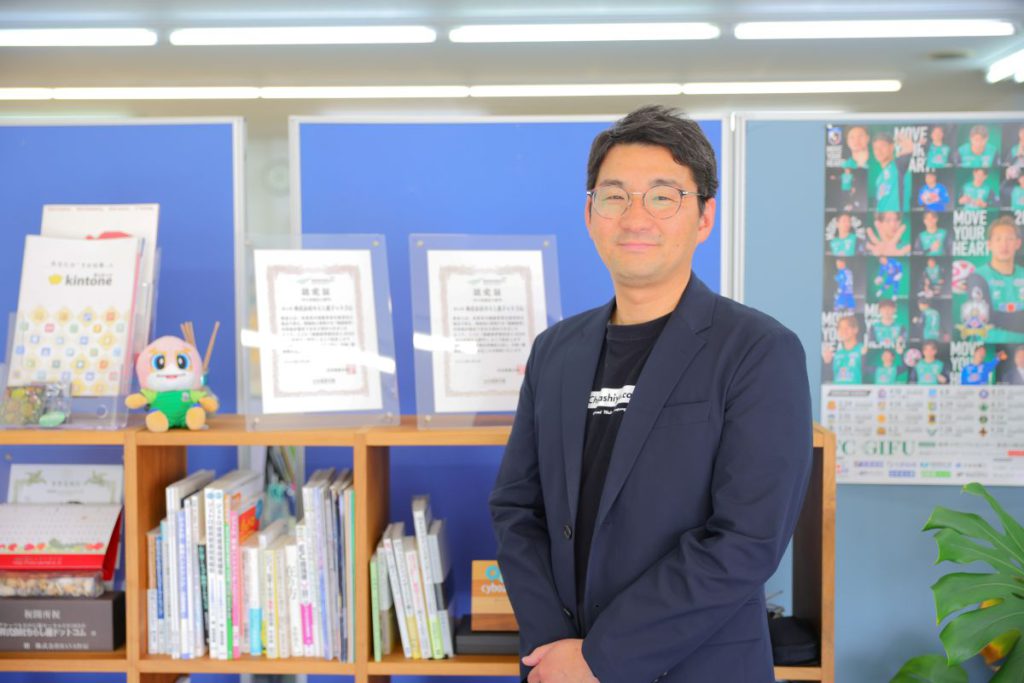
うん。正解。その通りですね。
アナログな受発注といえば、電話やFAXでのやり取りでしたよね。
ECサイトからの注文であれば、まだデータとして届くのでマシだと思うんですが、これが電話やFAXで受け付けた注文については、これまでの動画で説明してきた通り、ミスや受注漏れに繋がるケースもあります。
さらに、そのアナログ的に受け取った注文情報をもとに、例えば、Excelで出荷指示書にまとめたりするとこれはもう本当に大変ですよね。

なるほど。商品の型番を間違えたり、数量を間違えたりとか、本当に無駄な作業が増えてミスも多くなりそうですよね。
受注データから出荷指示書を自動作成
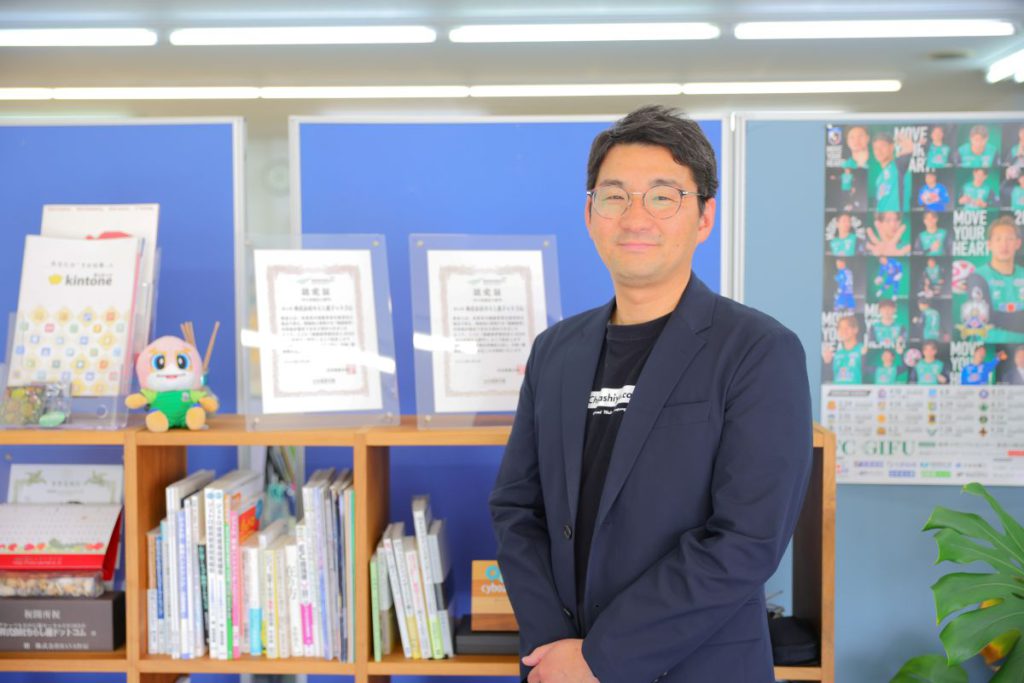
その通りなんです。
『BtoB』の受発注業務をもっと正確に、効率化していく必要が絶対にあると思うんです。
そのためには電話やFAXでのアナログの受発注から、『BtoB』のECサイトを通じてデジタルな受発注を行っていくということは当たり前として、その次の出荷指示といった業務もどんどん自動化していくことが必要になってくると思います。

そうですよね。でも受注データを元に出荷指示書のような社内指示を自動で作成することって簡単にできるんでしょうか?
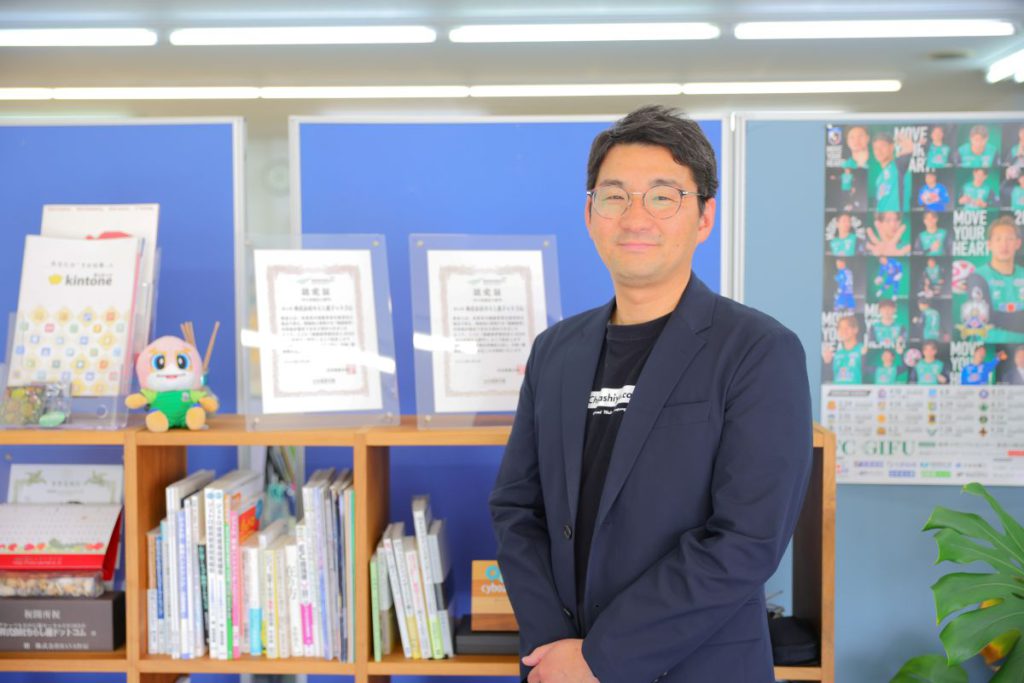
はい、それができるんです。
『BtoB ECサイト』を通じた注文であれば、例えば受注のデータをもとに、出荷指示書といったデータを自動で作成することができるんです。

おお、それはすごいですね。
入った注文のデータがそのまま自動で出荷指示書に変わるということは、ミスも減るし、Excelを作る手間からも解放されますね。
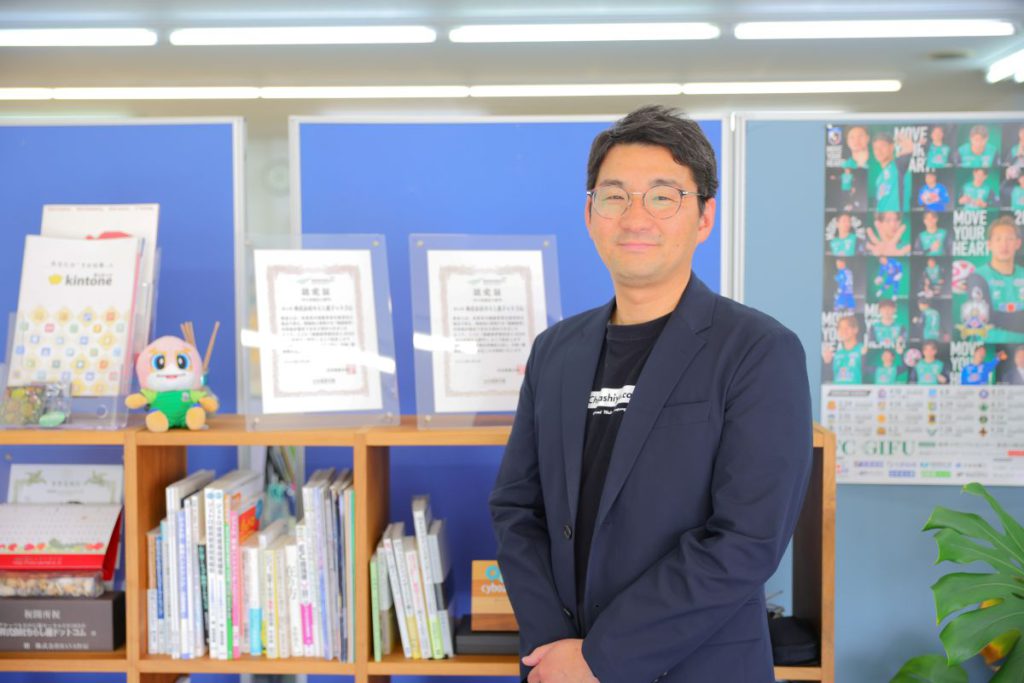
はい、その通りなんです。
そのまま画面を見て出荷作業を行ったり、出荷指示書のPDFファイルをダウンロードしたりできますよね。
ペーパーレスという視点ではお勧めをしていませんが、最悪、そのダウンロードしたPDFファイルを元に印刷ができるというような流れですね。
加工指示書・作業指示書への応用

なるほど。受注データを元に色々なデータに、変換できそうですね。
出荷指示以外だと、どんな社内業務に活用できるんですか?
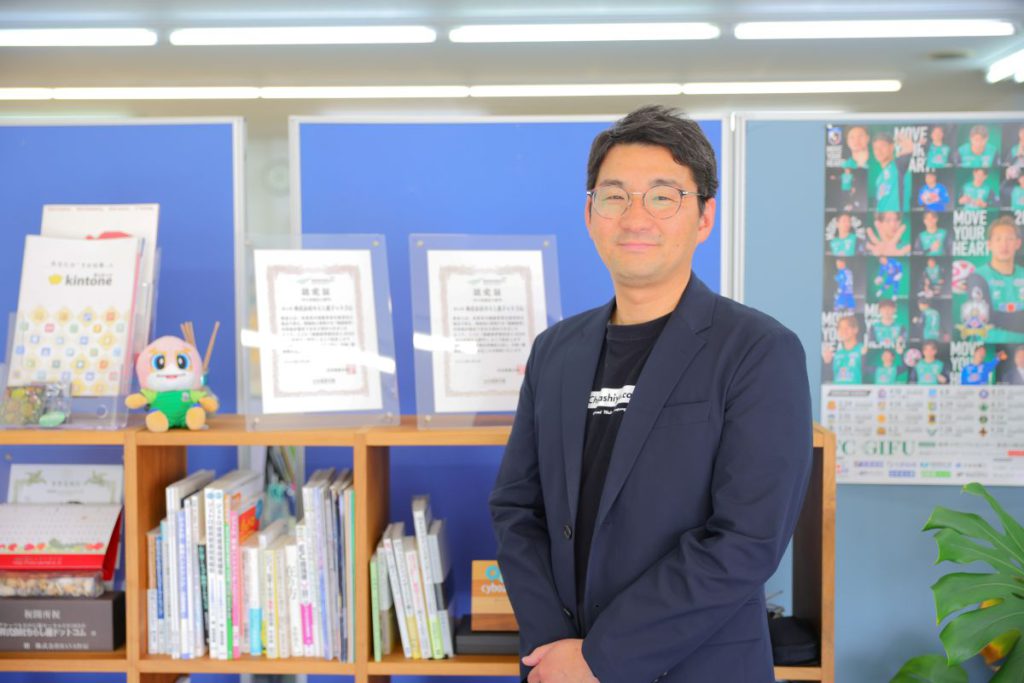
そうだね。
例えば、加工指示書とか作業指示書といった注文を受けた商品に対して加工作業が必要なものについては、関連の指示書が自動で作成・使用できるんじゃないかなと思います。

菊夫さん、今のその加工指示書とか作業指示書という話があったと思うんですが、例えば具体的にどのような商品がそういったものに当たるんでしょうか?
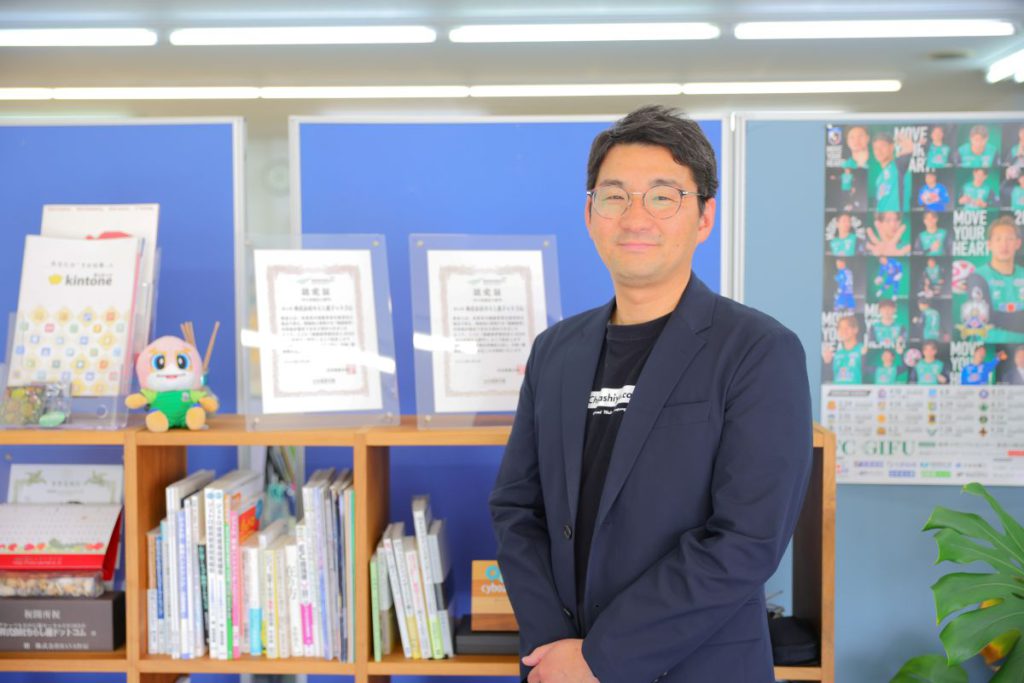
そうですね。
例えば、建築に使う建築資材で言うと、その資材を「5mの長さにカットして使いたい」という注文であれば、
その注文データをもとに「この注文が入った製品を5mにカットしてください」という、作業指示書・加工指示書のような形に、自動で変換していけるというイメージですね。

なるほど。
いわゆるお店とかでホームセンターとかだったら、店頭で注文すると担当者さんが要望通りのサイズにカットしてくれる。それをECでも実現していくということですね。
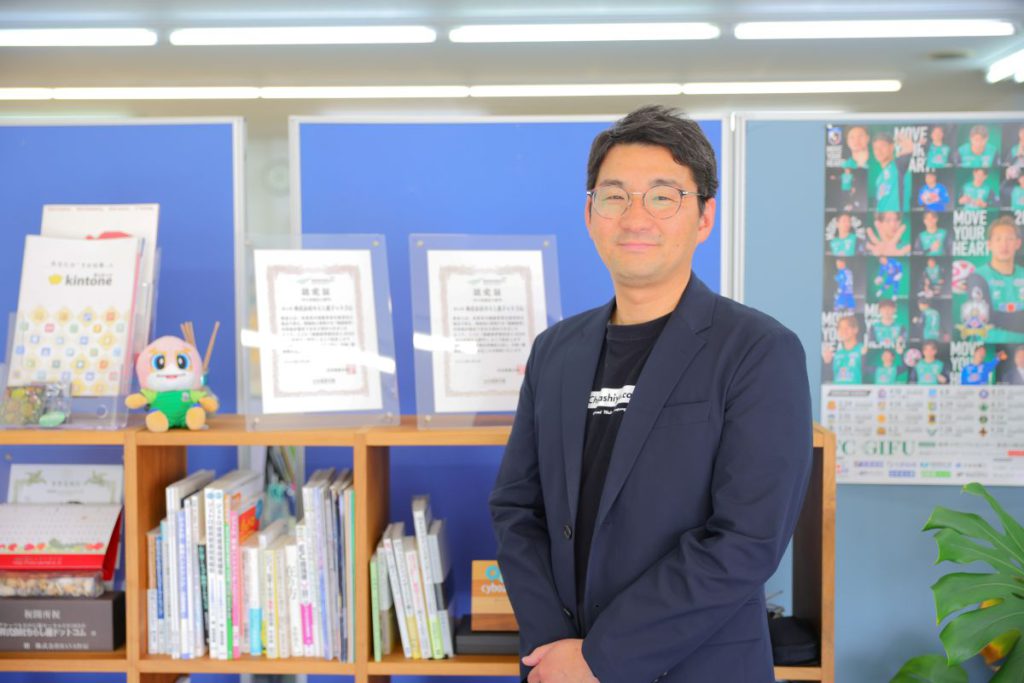
そうですね。まさにそのイメージですね。
『Biz-CUBE』のカスタマイズ性

でも菊夫さん、いわゆるこれらの機能っていうのは、サブスク系のECサービスでも、できそうなんですけが、そのあたりはいかがでしょうか?
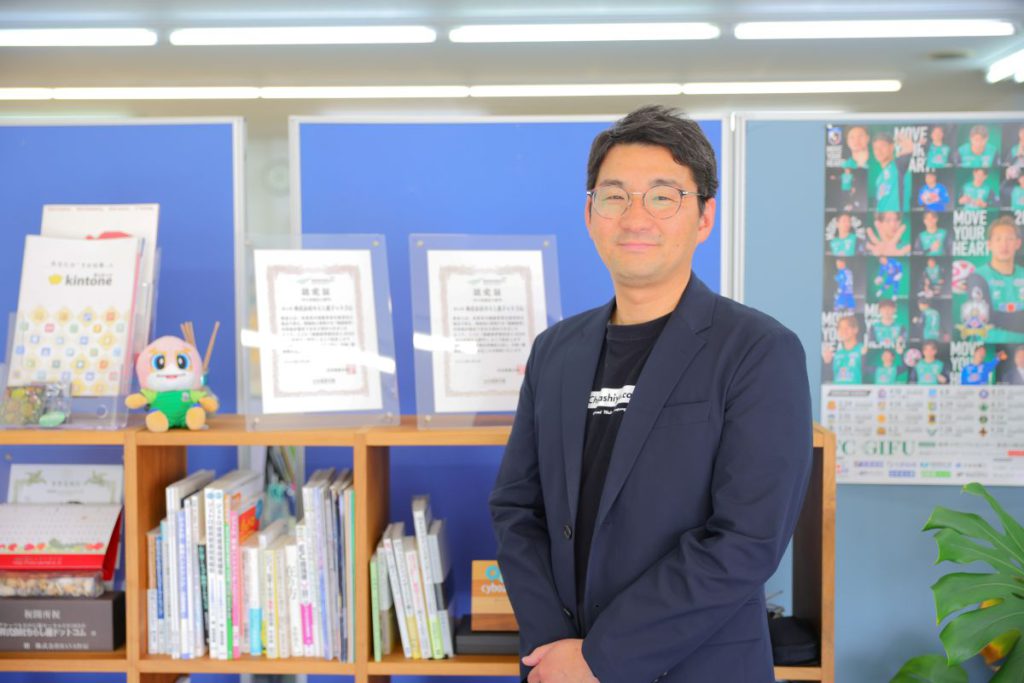
はい。もちろんそうですね。
いわゆるサブスク系の『BtoB ECサイト』サービスでも、注文のデータをもとに、出荷指示書にするとか、他の書類にするといった機能を持ち合わせてるサービスも当然あると思います。
ただし、やっぱり自社に必要なフォーマット・指示書であるとか、もっと記入する欄を増やしたいとか、そういった細かなニーズに対しては、ちょっと融通が効かないところも出ちゃうかなという風にいつも思います。
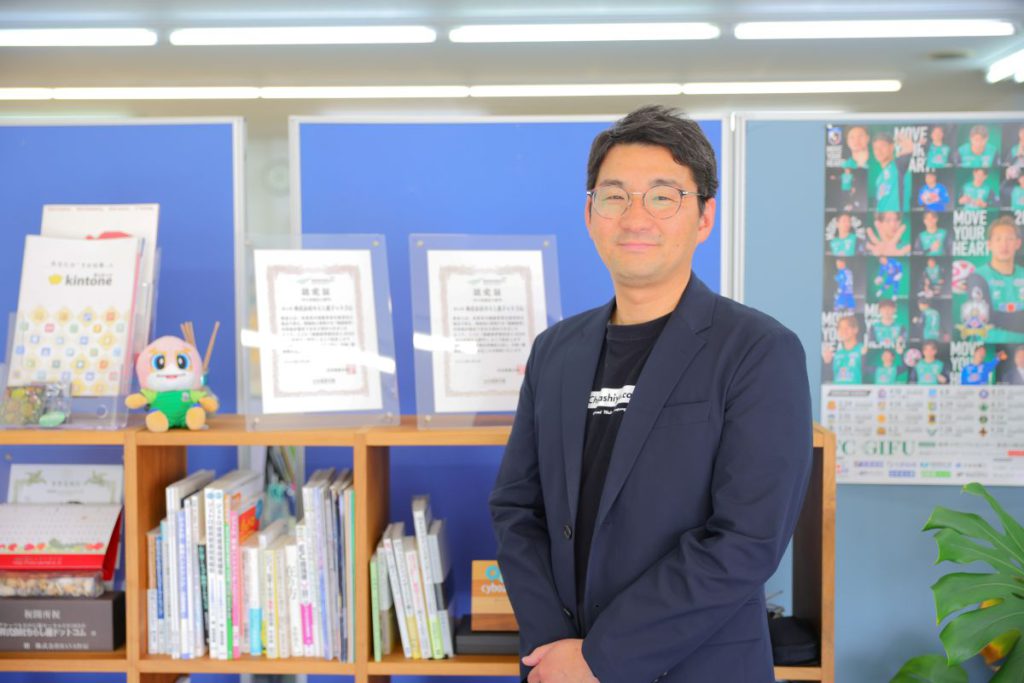
うちの『Biz-CUBE(ビズキューブ)』での構築であれば、そういった業務にフィットさせる部分であるとか、次の作業指示、加工指示の内容とかも業務に合わせて、カスタマイズしていけるという点が特徴になるかなという風に思います。

その柔軟にカスタマイズできるっていう点ですが、例えばどういったところを機能としてはカスタマイズされたりするんでしょうか。
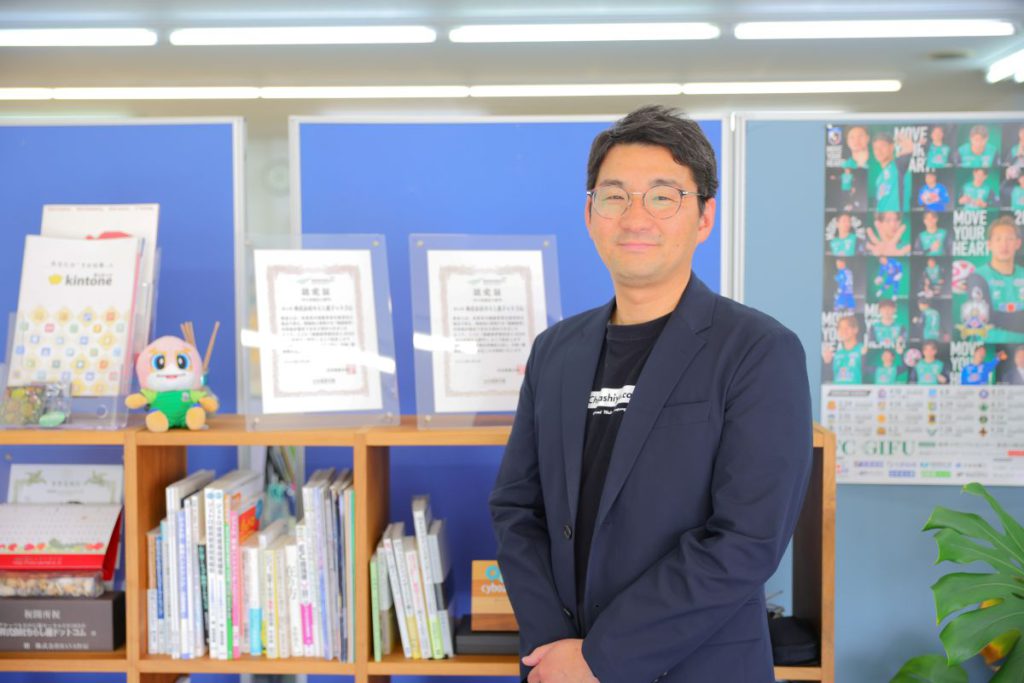
そうですね。
例えば、次の指示に対して、注意点を必ずコメント欄に追加したいとかですね。
あとは、注文日から自動計算して出荷日(期限)を自動で記載するといったような、現在の業務にフィットさせていくカスタマイズが可能かなという風に思います。
まとめ

なるほど。それぞれ会社さんの独自ルールにも対応できるというのが、強みということですよね。
その会社さんごとのやり方に合わせて、手作業でやっていた時間が、どんどん削減できるっていうこともいいのかなという風に今聞いてると思いました。
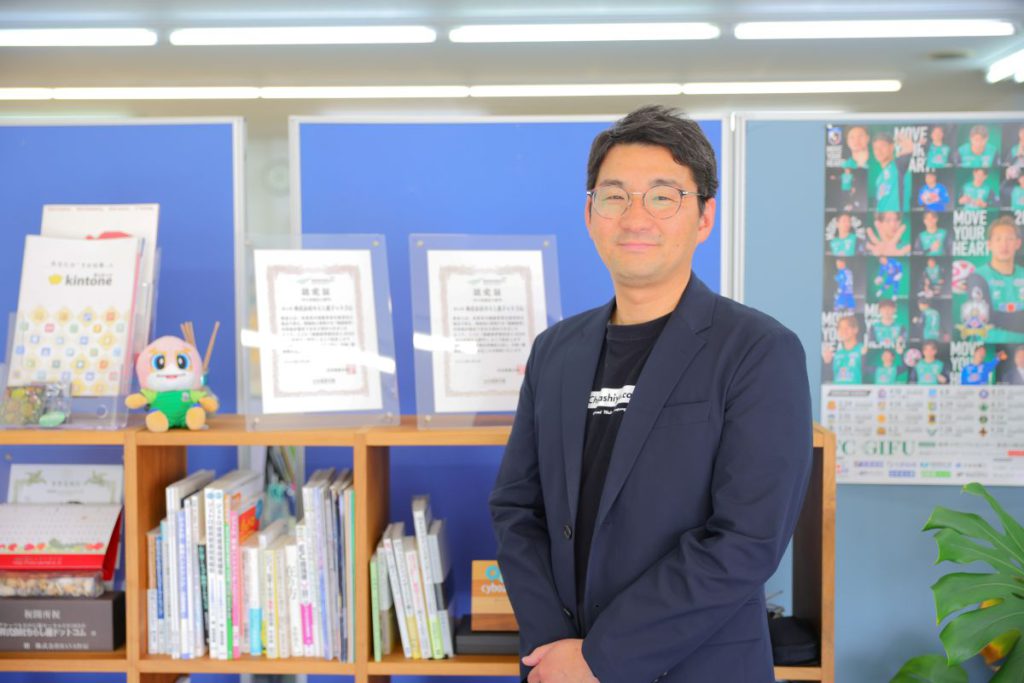
その通りですね。
人の作業が減るとその分ヒューマンミスも削減していくと思いますし、出荷とか、お届けミスとか、そういったクレームも減るでしょう。
結果的に顧客の満足度向上に繋がっていくと思います。

なるほど。
確かに単に、時短になるだけではなくて品質まで上げてしまう。そういったこともできちゃうということですね。
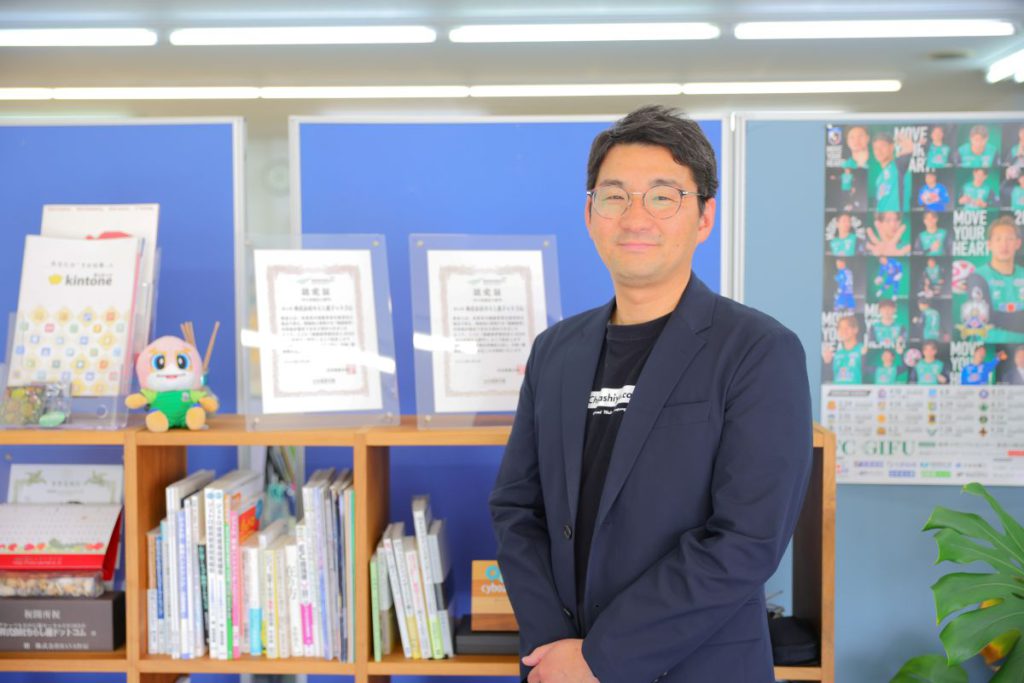
はい。その通りですね。
『BtoB ECサイト』を通じて、届いた受注データを元に業務を効率化自動化していくというところが『Biz-CUBE(ビズキューブ)』の強みという風に思っています。

わかりました。菊夫さん、今日も大変勉強になりました。ありがとうございます。
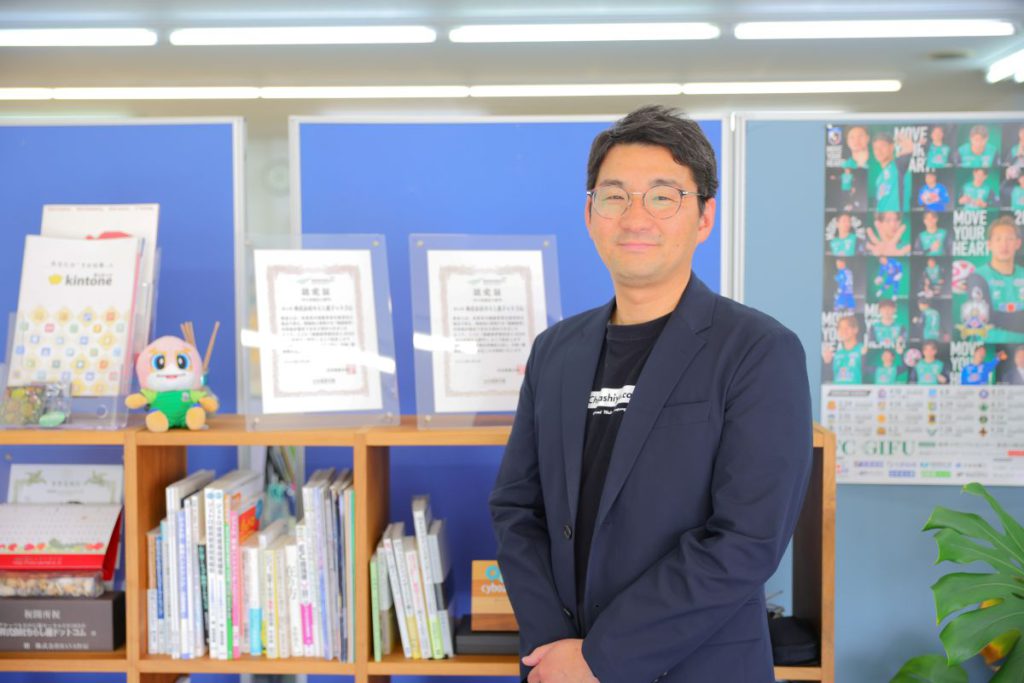
こちらこそありがとうございました。
BtoB ECサイトの構築・導入サポート・保守のご相談承ります
自社の業務に合った『BtoB ECサイト』を導入して業務を効率化したい、売上拡大を図りたいという方はちらし屋ドットコムにご相談ください。
お客様とお取引の受発注ルールをヒアリングして最適な『BtoB ECサイト」の導入・保守サービスをご提案致します。